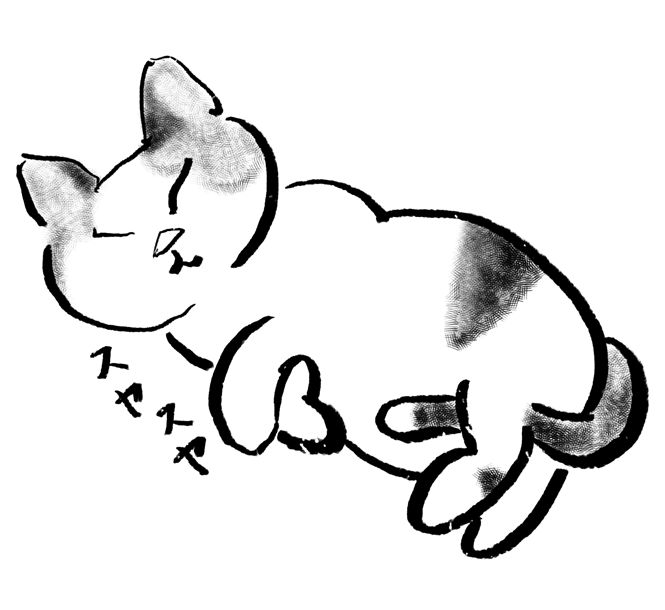・なぜ慢性腎不全になるのか?
なぜ慢性腎不全になるのか?
猫が慢性腎不全になりやすい要因を簡単に説明していきます。諸説色々とあるみたいですが、
・急性腎不全後に慢性化。
・猫の腎臓の糸球体は詰まりやすい。
・日々の食生活が原因で腎臓が悪化。
・先天性の腎形成不全や多発性嚢胞腎。
辺りが代表的な要因になると思います。
上から順に説明していきます。「急性腎不全後に慢性化」ですが、流石に猫に有害なアロマや植物由来や薬剤で急性腎不全になる子はここ最近は少ないと思います。猫飼いの方なら一度は耳にした猫にとって有害な事をする様な方はここを見て居ないと思います。となると急性腎不全に一番なりやすいのは尿道閉塞が考えられます。猫が尿路結石が出来やすい動物というのは有名ですが、他の動物よりオシッコを再吸収して水分を補いどんどん尿が濃縮されるのも原因の1つなのかもしれません。腎臓からの尿管や膀胱や尿道に結石が詰まりオシッコが出なくなった場合腎臓にダメージを負います。ただし、腎臓は2つあるため腎臓から出ている尿管2つが同時に詰まる確立は低いため片方の腎臓の尿管からはオシッコが出ますが片方は出ないため徐々にダメージが蓄積されます。ぶーにゃんも片腎が萎縮腎で機能していないので、去勢手術以外で動物病院に行ったことがない(ワクチン履歴も無い)環境で2014年8月〜2013年5月と2011年の3月〜保護されるまでの長い期間をケージ飼いで過ごしたので、どこかのタイミングで何らかの急性腎不全になったと思われますが、片方の腎臓が動いてない時点で慢性腎不全として診断出来るほど腎臓の数値が悪くなってる訳ですからその後の余命に大きく左右する事柄になります。
次に「糸球体の詰まり」についてですが、最近話題の東大のAIMタンパク質の研究でも発表されていますが、猫は糸球体が詰まりやすい動物というのが分かって来ました。糸球体は血液中の老廃物や塩分をろ過して尿にする働きがあるので、これが詰まると腎機能が悪化します。猫用としては新薬に分類されてますが1992年からヒト用も発売されているラプロスは55μgという高用量を1日2回猫に投与する事により糸球体への血流を増やし微小血栓の形成を抑制し炎症を抑えてくれます。如何に今残ってる糸球体を維持していくのかが慢性腎不全と上手く付き合っていく鍵になります。ぶーにゃんはラプロス発売日翌日から飲み続けてCRE4台から2年後には1.4という正常値まで落とせました。
日々の食生活ですが、一番始めに腎臓病と言えば塩分が思い浮かびますが摂取タンパク質と摂取リン量の制限が一番重要になります。なぜなら腎臓でろ過しきれなかった尿素窒素やクレアチニンが血液に溢れて身体に大きな負担をかけるからです。しかし猫はタンパク質を主に摂取して生きる動物なので摂取制限をするのは難しいです。摂りすぎないというのを念頭におきつつ、腎臓でろ過出来なかった分はサプリメントで吸着したり、そもそも腎機能を低下させないのが重要になってきます。同じく塩分も腎機能が落ちると排泄機能が弱くなるので高血圧や身体に水を貯める原因になるため出来るだけ低塩の食事を与えるのを心がけないといけません。
後は「先天性の腎形成不全や多発性嚢胞腎」になります。生まれつきや成長段階で腎臓が正常な状態で形作られて居ないため、腎機能が著しく低下している猫ちゃんが腎形成不全です。一般的にシャム・メインクーン・アビシニアン・バーミーズなどの種がなりやすいと言われてる様です。多発性嚢胞腎は腎臓に異常な嚢胞が出来て腎機能が悪くなる遺伝病でロシアンブルー・ヒマラヤン・ペルシャ・スコティッシュ・アメリカンショートなどで確認されています。加齢と共に嚢胞の数が増え、腎臓が肥大して行き腎機能は低下していきます。
他にも色々な要因で腎臓が急激に悪くなったりゆっくりと時間をかけて悪くなっていきます。現在実験的に幹細胞移植を行ってる病院や東大の新薬も2020,2021年頃には使える様になるみたいですが、動物病院にて処置及び処方されるのはほぼ確実です。かなりの高額医療になると思われます。限られた猫ちゃんしか使えない治療はそれが出来ない家族への大きな心の負担にもなるでしょう。そこまで悪化しないためにも日々の腎臓ケアを手を抜かずしてあげて今の状態を老衰まで維持してあげるのが理想です。その理想のお手伝いが出来たらと思っています。
通常の血液検査で慢性腎不全として診断される頃には腎機能の75%が失われています。そうなる前に見つける方法として2015年より血液検査を専門機関のIDEXXにてSDMA検査する方法があります。
→外部リンク 【SDMA: 腎臓病の早期診断】
検査費用は2000円前後ですが病院によって変わってきます。この検査により腎機能が25%〜40%失われた時点で数値による変動を確かめる事が出来ます。前述した通り、慢性腎不全とは如何にして悪くならない様に今の腎機能を維持するかが焦点なので、腎機能が落ちてきているのが早めに分かるとその分腎臓のケアを始める時期が早まるので余命が伸びます。
次に猫ちゃんの症状として慢性腎不全が現れる場合ですが、
1️⃣お水をたくさん飲む。のでオシッコもたくさん行く
2️⃣毛玉以外の嘔吐が増える
3️⃣食欲不振、食欲廃絶
4️⃣体重減少
5️⃣オシッコ粗相
6️⃣貧血
7️⃣口臭
8️⃣毛づやが無くなる
9️⃣元気が無い
と多岐に渡ります。1️⃣2️⃣4️⃣に関しては慢性腎不全の他に甲状腺機能亢進症や糖尿病でも同じ症状が有名なので慢性腎不全だと決めつけると他の病気を見逃す事もあります。
詳しく説明…
👇👇👇
1️⃣に関してぶーにゃんは1日500ml以上の水と10回近いオシッコでしたが、甲状腺機能亢進症も引き取った時から症状が顕著だったのに慢性腎不全の影に隠れて発見が遅れました。濃いオシッコがネフロン(糸球体)の低下から作れないため薄いオシッコを大量に出す事により体の中の老廃物を排出するため多飲多尿になります。
2️⃣の嘔吐については毛玉以外で吐く回数です。吐く回数が多いと脱水にも繋がるので注意が必要です。体力も使いますし…。
3️⃣慢性腎不全の子は食べる量が減ったり食べれなくなる事が多いです。食べたくても口内環境が悪くて痛くて食べられない事もあります。出来る事は食べれる他の療法食を探してあげる事、食欲増進剤を試してみる事、強制給餌でサポートしてあげる事です。
4️⃣病気になる前5kgの子の場合で書くと体重が50%減った場合危険水域になります。餓死寸前と言って良いでしょう。許容範囲は30%減までです。それ以上減っていく場合は 3️⃣で書いた何らかの対策が必要になります。病気に負けるのではなく餓死で負けるのです。餓死はとても辛いそうです…。
5️⃣オシッコ粗相はトイレ以外でオシッコをしてしまう事ですが、ぶーにゃんは前のお家の時は同居猫と反りが合わなかった様でオシッコ粗相は毎日あった様です。うちに来てからは一人になったのでかなり減ったのですが、そういったストレスとは別にトイレ以外での粗相が増えた場合慢性腎不全を疑う要因になるでしょう。
6️⃣慢性腎不全が進むと腎性貧血になりやすくなります。ふらつきや活動量の低下や食欲不振や水分摂取の低下にも繋がります。また心不全とも関係しており貧血が貧血を呼ぶ悪循環に陥ります。
7️⃣口臭は歯磨きがなかなか難しい猫ちゃんにはありがちですが、慢性腎不全が進むと尿毒症の症状としてアンモニア臭を口臭から感じると言われて居ますが、いつもの口臭が強めに感じる場合もある様です。ぶーにゃんは介護用スポンジに歯磨きジェルを噛ませて口臭チェックを行っていました。
8️⃣9️⃣完全に主観になりますが、飼い主さんが一番最初に気づけるハズです。毛づやが悪く元気が無い状態が続いてる時は様子見をするのではなくすぐ検査してみましょう。
👆👆👆
【病院での治療】
投薬と皮下輸液の2種類になります。透析も出来る所はありますが、猫ちゃんへのストレスやQOLの著しい低下、医療費を考えると現実的では無いでしょう。また、最近幹細胞治療を行う動物病院もありますがまだ情報は少ないので調査中です。
・投薬について
フォルテコール、ファルプリルなどのACE阻害剤と、セミントラのARB阻害剤と、ラプロスの経口プロスタサイクリン製剤が主な治療薬になります。 まずラプロス以外の3つのお薬について説明をしますと、どの薬も体全体の血管を拡張させ高血圧を抑える効き目があります。ACE阻害剤よりARB阻害剤の方が血圧を下げる効果は低いですが、猫ちゃんに尿蛋白が出ている場合セミントラが使われる事が多いです。3つのお薬全てが腎臓で主に代謝されるお薬なので、腎臓の悪い子に投与する時は新調に行わないといけません。
続き…
👇👇👇
ぶーにゃんも2017年4月まではファルプリルのみを飲んで居ましたが、ラプロスの追加でCREの上昇があったのでACE阻害剤は休薬にしました。その後は右肩下がりでCREが落ちていき正常値まで落ちた感じです。ACE阻害剤やARB阻害剤を使いたがる獣医師さんは非常に多いですが、その理由は今まで使ってきたお薬なので実績と対処がしやすいという所でしょう。ただし、ラプロスという後発の新薬が出た以上腎臓のために飲んではいるが腎臓に負担もかけているという状況はなるべく早く離脱すべきと思っています。
👆👆👆
次にラプロスについて説明します。このお薬は猫にとっては新薬ですが、人間用としてドルナーという名前で1992年から使われてきている古いお薬です。ラプロスが発売される前にドルナーを処方していた動物病院もありましたが、著効(お薬が良く効いてる状態の事)したという報告はありません。なぜならば、人間と猫の体重を考えて処方量をかなり減薬していたからとみています。猫の慢性腎不全治療薬として発売されたラプロスは55μgを1日2回与えて効果が実証されたお薬です。ドルナーは人間で1日の最高容量で360μg(1日120μgを3回)処方されます。単純な体重比で1/10に減薬すると36μgになるので、1回の投与量は18μgになります。前述しましたが、ラプロスの臨床データで効果が出たのは1回55μg(臨床時は60μg投与)です。1日で人間の体重の1/10の猫ちゃんに110μgという高用量を与える事で効果が出たお薬です。さて、効果についてですが、毛細血管の減少を抑える・血管を拡張させる・血栓が出来るのを抑制する・炎症を抑える効果があります。しかも体全体というより腎臓にピンポイントで作用します。腎臓への血流が増え、糸球体に詰まる血栓が出来づらくなります。また肝臓で主に代謝されるためお薬を飲むことにより腎臓に負担がかかるのが少ないです。
続き…
👇👇👇
まさに良いことずくめですが、ぶーにゃんの場合はお腹がゆるくなるという副作用が出ました(後に完全に元の💩になりましたが)。どの薬にも副作用はあります。ACE・ARB阻害剤もあります。むしろあっちはヒトでは慢性腎不全が進行した患者さんには投与してはいけないお薬に分類されています。高カリウム血症もあるし咳が出る副作用も多いです。お腹がゆるくなったら腸内環境をもっと良くしてあげてラプロスに耐えれる体作りや排便ケアをしてあげれば良いのです。後、ラプロスは慢性腎不全のステージ2,3に対して有効というデータが出ており、ステージ4以降の猫ちゃんではほとんど症状の緩和が見られなかったデータが出ています。慢性腎不全はステージ1がCRE1.6未満、ステージ2が1.6-2.8未満、ステージ3が2.9-5.0未満、ステージ4が5以上と言われています。悪くなりきってからでは効果の得られにくいお薬です。発売されて2年が経ち良好なデータも出ているのに未だに処方を頑なに拒む獣医師さんもいらっしゃいます。さっさと他の病院に移りましょう。今までどおりACE阻害剤ARB阻害剤を使ってて悪化しても新薬や新治療を拒む獣医師さんが保証してくれる訳でもありません。個人的な古い考えを新しい有効な治療を望む患者さんに押し付けないで頂きたい。
後、ラプロスを割ったり粉にして飲ませても良いという獣医師さんがいらっしゃいます。ラプロスの成分は刺激性がある劇薬指定なので錠剤にフィルムコーティングがされていますが、どういったお考えで割ったり粉にされているのでしょうか。また、上述しましたが、高用量にて効果がある臨床データから1錠を1日2回という処方量になっているのに、1日1回で良いとか半錠を1日2回とか獣医師さんの裁量で処方されている方も多いですが、低用量で効果があったという臨床データでもお持ちなのでしょうか?ただ服用しているという安心感のプラシーボ効果は暗示の効かない猫には無意味です。製薬メーカーの東レにも問い合わせしましたが、処方するのは獣医師さんの裁量なので強制は出来ませんとの解答でしたが、何のデータにも基づかない処方は考え直して頂きたいです。後、割線の無い錠剤は一錠中の成分量は一定ですが、半分に割った同士は一定ではありません。ラプロス1錠55μgを2つに割ったら27.5μgずつ分かれる訳ではありません。動物病院での処方は何かとヒト用のお薬を動物向けに割って容量を少なくして処方されますが、割れば良いという考えは無くしてほしいです。現実的に割らざるを得ないのはしょうがない事は分かりますが、動物へのお薬の処方は学術的データに基づいて行って欲しいです。後、1錠処方で100円、1/4処方でも100円とかアバウト過ぎます。
他にも言わせて貰うと、ラプロスは処方料が高いのでも有名です。元々が安いお薬では無いという所以もありますが、安い所は80円や100円で処方されてます。ぶーにゃんが看て貰ってた動物医療センターは150円、セカンドオピニオンの猫専門病院に至っては250円でした。Twitterのフォロワーさんの中には280円の方もいらっしゃいました。一体どれだけ搾り取ろうとお考えなのでしょうか。一生飲み続けるお薬や注射に非情な倍率で病院の利益を上乗せされると、それを負担出来ないご家庭の猫ちゃんは治療を受けれないですし、また治療してあげれない家族の心の責め苦にもなります。何のための動物医療なのでしょうか。動物の命を助けてあげて、その地域のペットを家族にされてる家庭が安心して飼い続けられる環境づくりもその地域に根ざしている動物病院の使命ではないでしょうか。年間保健所に収容される猫ちゃんが6万頭ほどいます。そのうち飼い主さんが出来るのが2万6千頭ほどで、残りの3万4千頭は殺処分されているのが現実です。余りにも高い動物医療は猫を飼う上で大きな障害になります。一過性の症状に対するお薬や手術や検査が高いのはしょうがないと思いますが、生きてる限り必要な治療に対して病院によって月3万円のお薬の所もあれば同じ薬を月9万円で処方されてる病院もあるという実態に納得は行っていません。自由診療ならブラックジャックみたいに何を要求しても良いという現状から、何らかの形で国の監査が入って欲しいと思っています。
ちなみにこの文章を書いてる私は今まで動物保護活動をしてきた訳ではありません。また今後も自分の人生の中で体力的・時間的に動物保護活動をする余裕は残念ながら抱えられません。その代りTNR活動をされてる所に支援物資や医療機器の寄贈は行っています。次に生まれ変わった時はボク自身が体を張るのでご期待下さい。
👆👆👆
・皮下輸液法について
慢性腎不全の猫ちゃんは脱水や尿毒症を予防するために状態によって毎日・隔日・数日置きに背中の皮と身の間に生理食塩水を入れてあげて治療します。上述しましたが、昔に比べて今は慢性腎不全も比較的早期に発見出来る様になったため、日常的に起きる脱水を皮下輸液で補うことにより慢性腎不全の進行を抑える事に繋がります。しかし皮下輸液は循環器系に負担もかけるので潜在的に心疾患がある子には気をつけてあげなければいけません。肺水腫や高血圧の原因にもなります。皮下輸液をすればする程体調が良くなるという事ではありません。脱水が見られる猫ちゃんに適切に適量を行ってあげるのが大切です。
続き…
👇👇👇
病院では背中に皮下輸液を入れる以外にゆっくりと静脈点滴で入れてあげる事も出来、こちらの方が効果も高く体への負担も少ないです。ただしお預かりや入院が必要なのでワンちゃんが泣き叫ぶ空間に独り置いていく事になります。そこら辺のストレスや入院費用も考えて病院でするのは緊急時の静脈点滴、日常的には自宅での皮下輸液と考えた方が現実的でしょう。難しい様に思えますがヒトも猫も慣れてしまえば自宅での皮下輸液はそれほど大変では無くなります。病院で皮下輸液をする場合、1000円台の所もあれば5000円台の所もあります。平均で3000円強といった所でしょうか。自宅でする場合、数百円〜で抑える事が出来ます。ただし病院によって生理食塩水のパックの値段や翼状針や点滴のラインやシリンジの値段が大きく違います。ボクの記憶ではテルモ生食500は150円もしなかったと記憶にあるのですが、病院によっては1500円で販売されてる所もあります。何がどうなると10倍の値段になるんでしょうか。160円のペットボトル飲料が1600円で売られるみたいな。夜間に急遽具合が悪くなって夜間診療を行ってる緊急病院で静脈点滴(生食)をして貰った知り合いはお会計で48000円かかったそうです。払えないなら治療しなくても良いんじゃよ。まさに金で命を買うが動物医療なのでしょうか。しかも買えてないし、対症療法だし。
さて皮下輸液には2種類あります。点滴であげる場合とシリンジで直接注入する方法です。ぶーにゃんには隔日で120-180mlをシリンジで直接入れていました。直接といってもシリンジに翼状針をつけてテープで固定してシリンジを押し込む訳で太い針を使う訳ではありません。ぶーにゃんの場合23Gというとても細い翼状針を使っていました。当然細い針は時間がかかるので嫌がるというかぶーにゃんはおとなしくしてる時間が決まっててそれを超すとカラータイマーが回ってフリーダムになります。なので50mlのシリンジに目一杯引いて60mlを2,3本入れるのが限界でした。たまに太い針を使われてる方もいらっしゃいます。使っている理由も分かりますし選択肢が無いのも分かります。しかし、太い針はより皮膚を大きく傷つけます。18Gなどの太い針だと処置完了まで短い時間で済むのも知ってます。猫ちゃんに刺す前にヒトに何万回も刺して来ました。分かってます・・・分かるんですが、なるべく細い針を使ってあげて下さい。猫ちゃんは他の動物より皮膚がんにかかりやすいと言われています。同じ所に何度も刺すと皮膚が固くなり最終的にタコという状態になってそこには打てなくなります。なるべく細い針で同じ所ではなく打つ所をずらしてあげて下さい。僕からのお願いです。
点滴を吊るして皮下輸液を行ってる方は特に太い針を使われてる方が多いです。細ければ細いほど点滴完了まで時間がかかるからです。そういった場合、点滴用加圧バッグ(インフュサージ)を試してみて下さい。猫ちゃんに常日頃行っている治療を漫然と行うのではなく、常にどうすればもっと負担を軽くして心穏やかに治療してあげられるか考えてあげて下さい。
病院での治療の所で自宅でする皮下輸液ケアについて書いてしまいましたが、皮下輸液に関しては後ほど専用のコーナーでより詳しく書こうと思っています。輸液パックは処方箋が要りますし種類や追加する薬剤なども獣医師の先生に判断して頂かなければいけませんから病院で頂かなければいけませんし。しかしそれ以外は何とでもなるのがネットの通販社会なので、後ほどそういったコーナーも作ろうと思います。
👆👆👆
・幹細胞治療やAIMタンパク質治療について
こちらに関しては皆さんがお聞きしてる内容以上の情報は持ち合わせていません。AIMタンパク質の治験を行ってる方から経口投与で与えてると聞いた位です。幹細胞移植に関しては1回13万円の治療で行ってる動物病院もあり割と身近になって来た治療法ですが、慢性腎不全に著効する様な治療法では無いですし何とも言いづらいのが現状です。
続き…
👇👇👇
またAIMタンパク治療も急性腎不全に対する特効薬という位置づけと思っています。慢性腎不全にも効き目はある様ですが、なかなか情報がアップデートされないのに危惧しています。AIMは2020年〜2021年治療開始を目標にされてる様ですが、いずれにしても動物病院で受ける治療になるでしょうから治療費が今から心配です。ぶーにゃんが生きていたら効果の見込める治療なら喜んで先頭を切って試していたと思います。しかしそれも叶わぬ夢になってしまったので、今頑張られてる方は今から貯金頑張って下さい(;`д´)
👆👆👆
長くなるので別ページにて解説しています。